2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ東京」は第二回の開催となります。
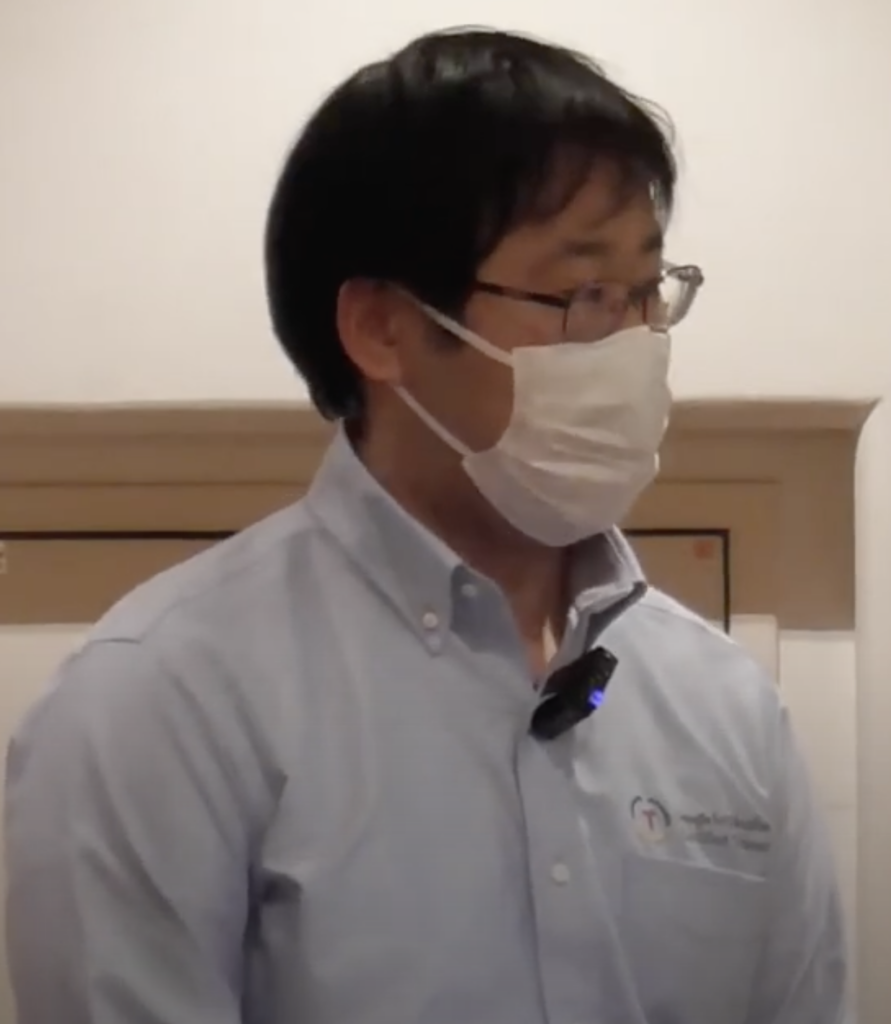
本記事では、第2回リアルゼミの中から、授業実践事例を発表した西武文理学園の笠原先生の実践をレポートします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。
1. ICT活用の歩みとデジタルシティズンシップへの接続
西武学園文理高等学校の国語科教諭・笠原諭先生は、同校で取り組まれているICT活用と、それに伴うデジタル・シティズンシップ(以下、DC)教育の展開について、現場目線から実態を交えて具体的にお話しいただきました。
笠原先生が冒頭「やっとここまでたどり着いた」と語るように、同校におけるICTの導入は決して一足飛びではなく、長年の試行錯誤の結果だと振り返ります。新型コロナウイルス感染症による一斉休校の時期には、教育現場でICTの必要性が痛感され、同校でも2021年から本格的にChromebookの導入を開始しました。年次進行での対応が進み、Wi-Fi環境の整備とともに、ようやく「当たり前にChromebookを開く授業風景」が定着しつつあるそうです。
しかし、笠原先生は「ICT機器が整ったからといって、それがそのまま教育の質に直結するわけではない」と語ります。機器や制度の導入と並行して、教員自身の不安や懸念にも対応しなければならず、校内での丁寧な対話と情報共有が欠かせなかったそうです。教員同士が「これが心配」「こういうトラブルが起きたらどうするか」といった率直な疑問や懸念を出し合える雰囲気をつくり、それに応じた勉強会や研修も重ねられてきました。
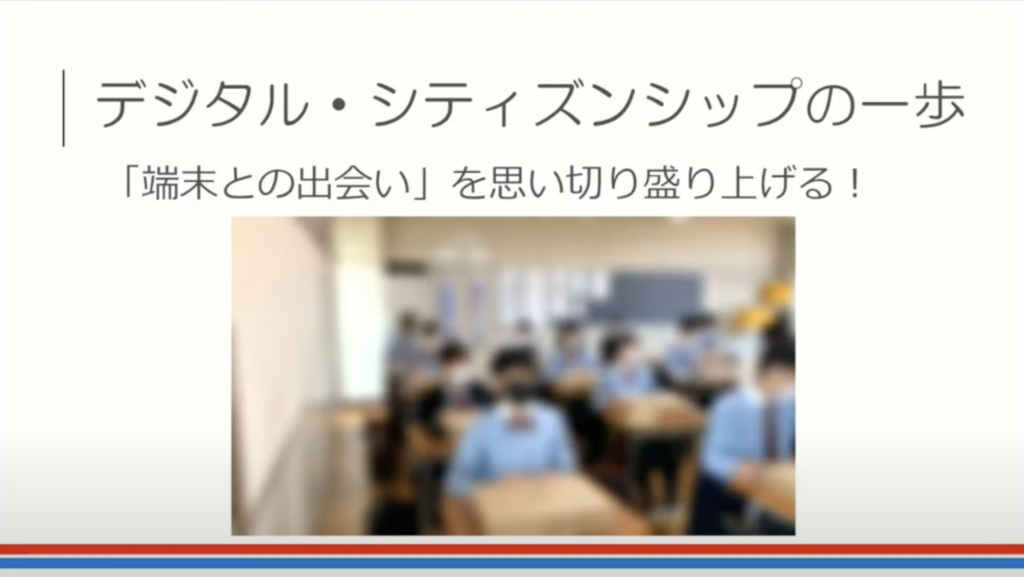
そのうえで、DC教育の導入にあたっては、「生徒に自信と責任を与える」ことを重視してきたといいます。たとえば、生徒に端末を配布する「開封の儀」では、教員が儀式的な演出を行うことで、生徒に対して「これから新しい学びが始まる」「自分の端末を自分の責任で使っていくんだ」という気持ちを自然に芽生えさせようと工夫されました。これはDC教育における第一歩であり、「スタートの場面をどう演出するか」がその後の学びの質に影響を与えるという、教育的な示唆に富んだ取り組みです。
2. 教科としての国語とDC教育の融合実践
笠原先生は、「DC教育は探究や総合学習だけでなく、教科教育の中でも実践できる」という立場から、国語の授業の中で行ったDC教育の取り組みを紹介されました。
国語という教科は、情報活用能力や他者との対話、表現力といったDCと深く関係する資質・能力を含んでいます。笠原先生の授業では、Common Sense Educationの教材やSTEAMライブラリのワークを取り入れながら、「SNSでのやりとりにおけるジレンマ」や「ネガティブな投稿にどう反応するか」といったテーマについて、生徒が主体的に考え、発言し、記述する活動を取り入れていました。
特に印象的だったのは、「親しい友人がSNSでネガティブな投稿をしたとき、どう反応するか?」という問いに対する生徒の多様な反応です。ある生徒は「共感していいねを押さなければならないように感じる」と語る一方、別の生徒は「それは逆に深刻さを増幅させる行為ではないか」と意見します。笠原先生は、こうした発言の背景に「生徒たちが現実の人間関係を維持するために、SNS上でも配慮や忖度を行っている」という事実があることに注目します。
このように、生徒たちは単に「情報モラル的に良い行動」を知っているのではなく、実際の人間関係の文脈の中で葛藤し、選択しているというリアルな実態があります。そのため、DC教育では単純な善悪ではなく、「どうすればより良い関係性や社会の中で行動できるか」という視点を育てる必要があると笠原先生は説きます。
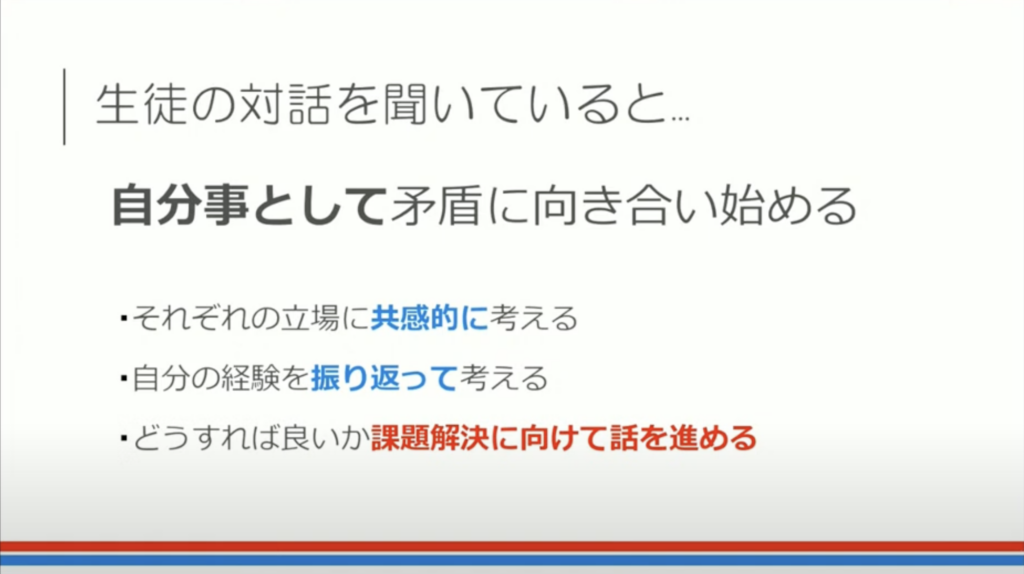
また、実践の中では、STEAMライブラリに収録されている「10歳の主人公が、いじめによるつらい経験からSNSの規約を破ってでも情報発信するようになる」という物語教材を使用されていました。生徒たちは、主人公の気持ちを想像し、自分だったらどう対応するかをグループで対話しながら深く議論していました。発言の一つひとつが、単なる感情論ではなく、具体的な社会的・倫理的な視点を伴っており、まさにDC教育における実践力の一端が表れていたと感じられます。
3. 生徒の主体性を軸にした校内文化の変容と課題
笠原先生は、DC教育の根幹にあるのは「生徒の主体性」だと繰り返し述べています。その上で、「端末は管理されるべきもの」ではなく、「自分で学びを構築するための文房具」だという認識を持たせることが、持続的なICT活用につながると語られました。
たとえば、授業中に生徒たちが自然とGoogle Meetでグループディスカッションを始めたり、チャットで意見を交換したりといった姿は、教員の指導を超えて「文化として定着した活用」の一例です。また、席替えの際にくじ引きアプリを使って公平に抽選を行うなど、日常的な学校生活にもICTを活かす工夫が生徒から自発的に生まれているとのことでした。
こうした変化の背景には、初期段階での丁寧な対話と、授業の中での小さな成功体験の積み重ねがあります。「探究の時間は失敗しても大丈夫」「最初はうまくいかなくても、チャレンジしていこう」といった風土が、教員と生徒の間に共有されているのです。これによって、生徒が「試行錯誤を通じて自分の学びを構築する」という姿勢を育てることができています。
一方で、今後の課題としては、「著作権や個人情報の扱い」など、より高度なリテラシーが必要な領域での指導の在り方が挙げられます。また、保護者との連携の必要性も強調されており、今後は家庭との情報共有を進めながら、保護者とともに子どものリテラシーを育てる環境づくりが求められると語られました。
そして、DC教育の究極の目標は、「社会に積極的に関与する力を持ったデジタル市民を育てること」にあります。笠原先生は、「現在はリテラシー教育の土台づくりの段階にあるが、今後は『社会を変えていく』という本来のDCの意義にも踏み込んでいきたい」と意欲を語って講演を締めくくられました。
