2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ広島」は第五回の開催となります。本記事では、第5回リアルゼミで行われた上智大学 教授 那須正裕先生とJDiCE副代表理事 の芳賀 高洋 の対談の概要をお届けします。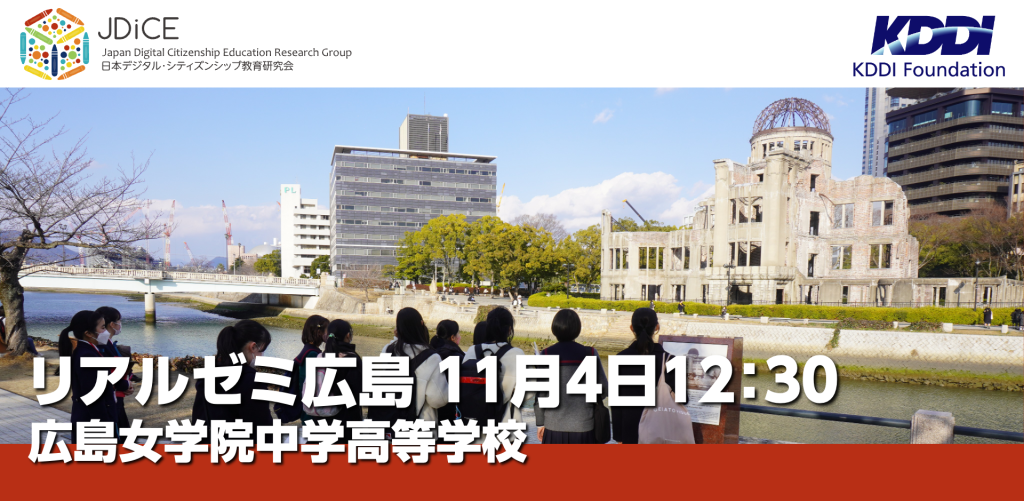 今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。
今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。
「言葉が知られていない」から始まるリアルな課題感
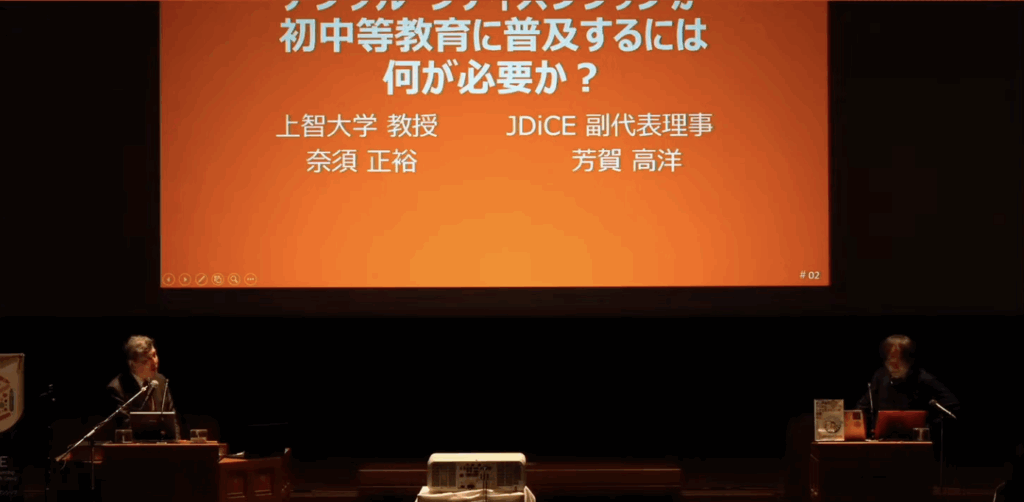
那須正裕教授による基調講演の直後に、芳賀高洋氏(JDiCE副代表理事)と「デジタル・シティズンシップが初等中等教育に広まるには何が必要か」というタイトルで対談が行われ、研究者と現場の教育支援者という立場から、それぞれの視点で語られる実践のリアルと理論の橋渡しが大きな見どころとなりました。
冒頭、芳賀氏は「那須先生のお話は、デジタル・シティズンシップという言葉こそ出てきませんでしたが、まさに私たちが大切にしている理念と一致している」と語ります。例えば「自立した市民の育成」「学習起立ではなく学習自律」など、那須教授が講演中に多用していたキーワードは、研究会の中でも繰り返し使われてきたものであり、その本質において理念は完全に重なっているという認識が共有されました。
しかし一方で、芳賀氏が全国の教員研修で実施しているアンケート調査によると、デジタル・シティズンシップという言葉そのものの認知度は、依然として極めて低いという実情も浮き彫りにされました。約1割程度の教員しかその名称を「聞いたことがある」と答えず、実際に実践の中で活用できると答える層はさらに限られているとのことです。
このギャップに対し、那須教授は「名前を知ってもらうことが目的ではないが、一定の共通言語がなければ社会的な動きにはならない」と冷静に分析します。つまり、「DC教育的なことはやっているが、それがDC教育だと認識されていない」という断絶を埋めていく必要があるということです。
また、ギガスクール構想によって急速に端末が普及した一方で、「使い方がわからない」「トラブルが怖い」という現場の不安が、デジタル活用の壁となっている現実も対談で共有されました。芳賀氏は、「多くの教師が、ICT活用が“子どもを統制できなくなるかもしれない”という恐れと直結している」と話し、その不安をどう乗り越えるかが鍵だと訴えました。
教科や制度を超えた“教育の本質”から始める
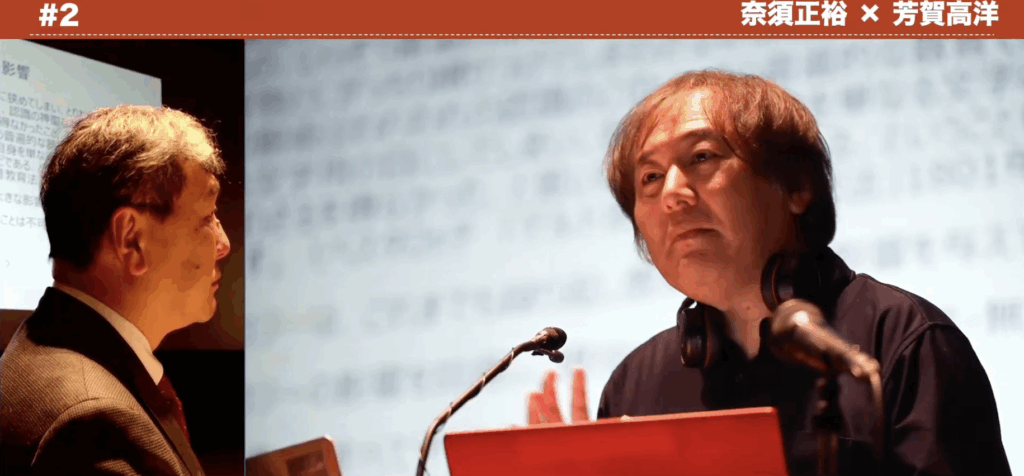
対談では、デジタル・シティズンシップ教育が「どの教科で教えるべきか」という、現場からよく寄せられる疑問にも触れられました。芳賀氏は「よく質問されるのが“これは社会科ですか? 道徳ですか?”というものだが、それは実は問いの立て方がズレているのでは」と提起します。これに対し那須教授も、「学習指導要領においても、すでに“教科と横断的な学習の視点での教育課程編成”が強調されている」と応じました。
つまり、DC教育は「特定の教科で教える知識」ではなく、学校教育のすべての営み——教科指導、学級経営、学校行事、さらには地域や保護者との関係性の中に埋め込まれていくべき“教育の姿勢”そのものであるという合意が示されたのです。
那須教授はさらに、日本の学校において「教育課程(カリキュラム)」という言葉がしばしば誤解されている点にも言及しました。従来、教育課程は教科ごとの指導内容を単にバインダーのように綴じ合わせたものと捉えられてきましたが、本来は「子どもたちに必要な経験の総体」として、学校全体で設計されるべきものです。
この「教科主義からの脱却」は、DC教育を進めるうえで不可避のテーマです。芳賀氏は「例えばDC教育は道徳でやっておけばいい、といった発想では、実態の変化に対応しきれない」と指摘し、「学校生活のすべてを通じて育まれる全領域道徳のような在り方が、むしろDC教育に近いのではないか」と述べました。
さらに、那須教授は「子どもを信じ、委ね、共に悩む」ことの重要性を繰り返し強調します。「教育は管理するものではなく、信頼と問いかけの中にこそ育ちがある」と語り、これはまさに芳賀氏の「アップスタンダー(立ち上がる市民)」を育てるという言葉と通底します。
お互いの視点の重なりに、会場にいた多くの教育関係者も深くうなずいていました。
言葉と文化の“土壌”を耕すことから始めよう
対談の終盤、話題は「ではDC教育をどう広げていくか」という実践的な論点へと移っていきました。ここでも焦点となったのは、“言葉”と“文化”の力です。那須教授は、「学校文化というのは、強い同調圧力のもとにある。それを解きほぐすには“問い”と“対話”の文化が必要」と述べました。
芳賀氏も、「例えば授業中に“それって公共空間でのふるまいとしてどうなの?”という一言を、日常的に子どもたちと交わせるようになることが、文化の定着への第一歩」と語ります。つまり、「情報モラルだから」「DC教育だから」と構えるのではなく、“市民として生きるための判断やふるまい”を、教師も子どもも自然に語れるような土壌づくりが必要だということです。
また、芳賀氏は「情報モラル教育とDC教育は、価値観の対立として語られがちだが、対立させるのではなく、補完的に捉える必要がある」と述べます。これまでの情報モラル教育が果たしてきた役割を否定するのではなく、DC教育によって視野を広げ、より未来志向の教育へと進化させていくという、ポジティブな接続が大切だということです。
対談の最後には、那須教授が「これは道徳教育とも重なる話」として、道徳の新しい方向性を示す「子どもに“望ましい価値”を言わせるような指導は避けるべき」という改善指針を紹介しました。まさにDC教育は、「答えを教える教育」から「問いに共に向き合う教育」への転換点にあるというメッセージでもあります。
芳賀氏もまた、「すべての子どもにデジタル環境がある時代だからこそ、その使い方を“ともに考えよう”という構えが教育現場に必要。教師が正義の代弁者になるのではなく、対話の伴走者になることが大切です」と力強く締めくくりました。
この対談は、理論と実践、学校と社会、個と集団をつなぐ、まさに“架け橋”のような時間となりました。デジタル・シティズンシップ教育が「普及する」ために必要なのは、新しい制度や教材よりも、まず「問いかけ」と「信じること」なのだと、改めて実感させられるセッションでした。
