2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第六回の開催となります。
本記事では、第6回リアルゼミから、基調講演を担当した小川修史先生(兵庫教育大学)、澤栄美氏(熊本市教育委員会・スクールカウンセラー)、古田翔太郎先生(熊本市立五福小学校)による鼎談の概要をお届けします。
子どもの「空気を読む力」をどう捉えるか
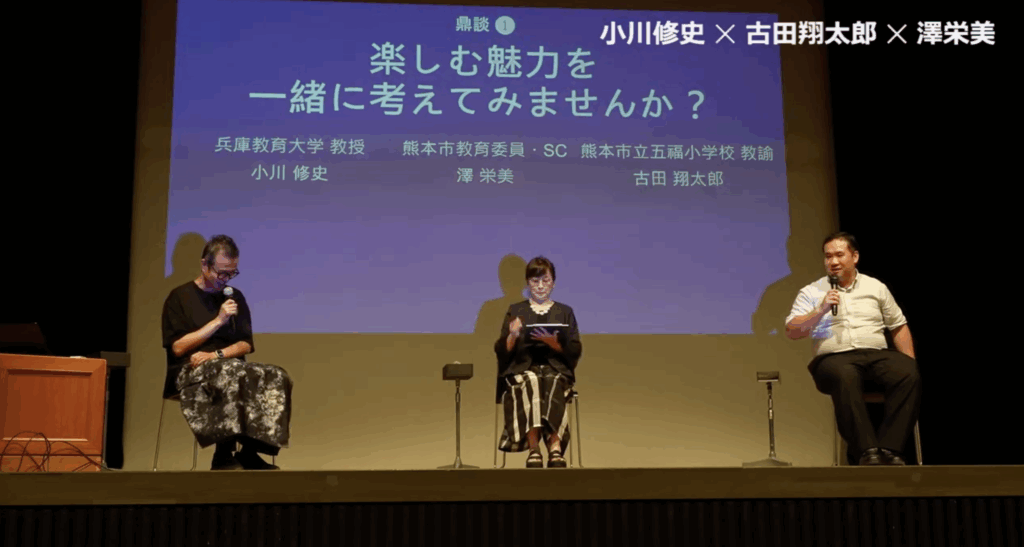
鼎談の冒頭、小川修史先生が語ったのは、基調講演の延長線上にある問いとして「空気を読むことは、子どもにとって本当に必要な力なのか」という視点でした。小川先生は、「空気を読む」という表現に対して、「それを前提とする社会構造が、時として子どもの自由な表現や行動を抑制してしまうことがある」と指摘します。そして、空気を「読む」こと以上に、空気を「創る」ことの重要性を強調しました。
これを受けて古田翔太郎先生は、自身の指導経験を踏まえて、「空気を読む」という行為が子どもたちにどう影響しているかを具体的に語りました。たとえば、「みんなの前で発表したいと思っていても、周囲の反応を気にして言えない」「発表したら『目立ってる』と陰口を叩かれる」といった事例に言及し、「読みすぎることで“行動の自由”が奪われる」実態を共有しました。さらに、自身が担当する通級指導教室では、「空気を読まない」と見なされがちな子どもたちに、どう関わっていくべきかを常に考えていると述べました。
このような問題意識に対して、澤栄美氏は「空気を読む力」に対する社会的価値観を問い直す必要があると語ります。澤氏は養護教諭やスクールカウンセラーとしての経験から、「空気を読めない=問題がある」というラベリングが、子どもたち自身を苦しめていることがあると指摘しました。そして、「空気を読む・読まない」ではなく、「自分と他者の気持ちに気づく力」や「それを表現する方法の多様性を認めること」が大切だと述べました。
鼎談では、空気を読むことが強制されるような教育環境が、かえって子どもの社会性を損ねてしまう可能性があること、そして「共に生きる力」を育てるためには、空気を“読む”ことに加え、“創る”側の視点を子どもたち自身にも持たせる教育が求められているという共通認識が見えてきました。
失敗を受け止める環境と“しんどい”を伝えられる文化
鼎談の中盤では、「子どもが“しんどい”と言える環境づくり」について、三者が実践例を交えながら語り合いました。小川先生は、ある中学校での放送活動の事例を紹介しました。発達特性をもつ男子生徒が「発表をやりたい」と希望し、教員たちは不安を抱きながらも、それを受け入れて任せた結果、彼はきちんとやり遂げ、仲間たちから拍手で迎えられたのです。この事例は、「空気を読む」ことを求めるのではなく、空気を共に創ることで成功体験を得られた好例であり、教師の“我慢”や“信頼”の大切さを象徴していると語られました。
続けて澤氏は、失敗を未然に防ぐ教育から、失敗を「共有し、乗り越える」教育への転換が必要であると述べました。とくに、「転ばぬ先の杖」のように、大人が子どもを囲い込んでしまう状況では、子どもが自分の気持ちや限界を把握しにくくなります。その結果、大学生や社会人になってから不適応や精神的な負担として現れることがあるという臨床的な観点が示されました。澤氏は、「“しんどい”と言える環境があるかどうかが、その後の人生の分岐点になる」と強く語ります。
古田先生は、自身が担任をした6年生の事例を紹介し、クラスでメディアとの付き合い方を話し合う授業を通して、「自由に使いたい」という本音と、「自分ではやめられない」という葛藤があることを、子どもたち自身が語り合えるようになったと述べました。教師が一方的にルールを課すのではなく、「自分たちで決めて、自分たちで守る」という自主性を重視した結果、「自分でやめようiPad」という標語がクラスで生まれ、行動に変化が現れたといいます。
また、澤氏は「自律とは“上手に助けを求められること”である」という心理学的定義を紹介し、助けを求められる関係性こそが、インクルーシブな教育の基盤であると語りました。大人が先回りしない、失敗を受け止める、しんどいと言っても大丈夫――そのような文化と環境が、ICTやデジタル・シティズンシップ教育を活かす土壌になるのだという三者の認識が、深く共有されていました。
学校と社会をつなぐ「共創」の教育へ
鼎談の最後のテーマは、これからの学校教育が目指すべき「共創的な学び」の在り方でした。小川先生は、デジタルシティズンシップ教育が目指すべきは、「教える教育」ではなく、「一緒に考える教育」であると強調します。教師が子どもに何かを伝えるという一方向の関係ではなく、教師もまた社会の一員として、子どもと共に考え、共に学ぶ存在であるべきだと語りました。
この視点に立ったとき、ICTやデジタルツールは、「効率化」や「利便性」のための手段ではなく、「対話」と「共創」の触媒としての役割を果たします。古田先生は、「授業中にタブレットを使っている子どもたちの様子を見て、教師が『遊んでいる』と誤解する場面もある」と語り、その誤解が教育の変革を妨げる可能性を指摘しました。実際には、タブレット上で自分の考えをまとめたり、発表の準備をしたりと、「学び」のプロセスの中にICTは深く根づいているといいます。
澤氏は、子どもたちの声をきちんと聴き、その言葉の背景にある気持ちに寄り添うことの重要性を再度強調しました。たとえば、「ルールを守れない子」と見るのではなく、「なぜ守れないのか」「どうしたら守れるのか」を一緒に考えることで、子どもたちは自分を責めることなく、成長への一歩を踏み出すことができるといいます。
小川先生は、締めくくりとして「教育とは“信じること”」だと語りました。子どもの可能性を信じ、大人自身も常識のタガを外しながら、自ら学び、挑戦し続ける姿勢を見せることが、子どもたちにとって何よりの教育になる。そのうえで、テクノロジーと人間性、教育と環境の掛け合わせによって、「楽しくて、挑戦できる、そして尊重し合える学びの場」を創り出すことが、現代の教育に課された責任であると結ばれました。
