毎月1回、ゲストとDC研究会のメンバーが語り合う「DCオンラインゼミ」。初回のゲストは島根県雲南市立吉田中学校 の 谷口 将人さんをお招きし、実践発表を行なっていただきました。本稿ではその概要をお伝えします。
今後、動画のアーカイブを有償で配信することも検討しております。以下の概要を読んで興味が出てきたという方は、JDiCE事務局までご相談ください。
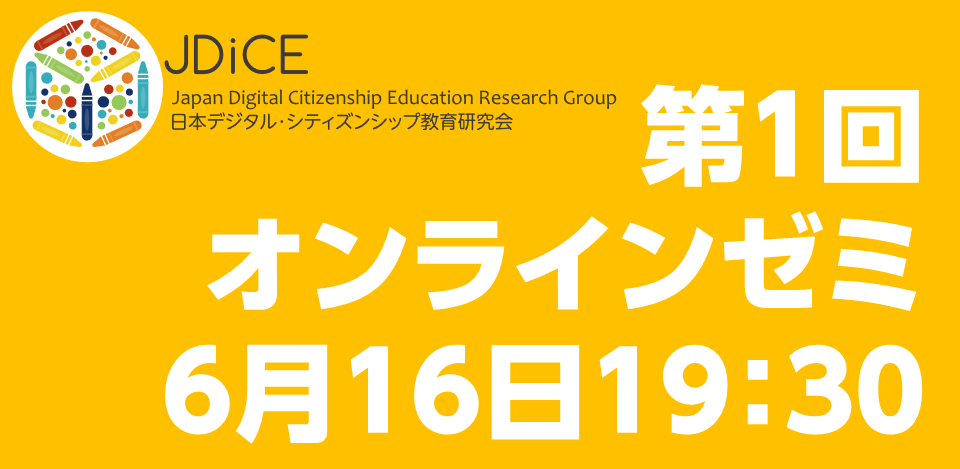
小規模校だからこそ実現する「親子で学ぶ」メディアリテラシー
島根県雲南市立吉田中学校の谷口将人先生は、2年生を対象に「メディアバランス」をテーマとした授業について報告が行われました。全校生徒30名という小規模校ならではの家庭的な雰囲気を活かし、保護者と生徒が共に学びを深める機会を重視したそうです。
1年生の時点で行われた導入的な授業に加えて、書籍『デジタル・シティズンシップ プラス』に掲載されている小学校高学年向けの実践を参考に、メディアとの付き合い方を親子で考える授業を実施。その成果を踏まえて、今回の授業では「自分のメディア習慣を見つめ直す」ことを目指し、Yチャートの作成や、メディアの特徴に基づいた「3つのデザイン」への分類活動が行われました。生徒たちは、テレビ・ゲーム・スマホ・SNS・読書など、自分が普段接しているメディアを棚卸しし、特にオンライン上のアプリやゲームに仕掛けられた依存的デザインやフィードバックループ的デザインに対する自覚を深めました。
授業は参観日と同時開催とされ、親子でワークシートに取り組む形が取られました。親と子が対話を通じて「自分にとってのメディアの意味」や「利用する時間のコントロール」について考えもらう、双方向的な学びを行いました。
2. 自己理解と自己調整を促す「メディアとの付き合い方」の再設計
谷口先生は、生徒が「他者から指導される対象」ではなく、「自分自身の生活を主体的に捉え、調整する存在」として扱うことを意識したそうです。授業では、依存的・フィードバックループ的・人間的という三種のメディアデザインの視点を使い、自分がなぜ特定のメディアを使っているのか、どのような影響を受けているのかを可視化しました。
生徒が自らの行動を素直に振り返り、それを言語化する。例えば、ポケモンゲームのレベルアップや報酬によって行動が促されていると書いた男子生徒は、そのデザインが自分に与える影響を理解し始めていました。また、「Twitterで漢字が読めるようになった」「Googleで知らないことを調べられる」など、人間的なデザインを肯定的に捉える声も多く、メディアを一律に悪とせず、その価値を見極めようとする姿勢が育まれていました。
授業の締めくくりには、「バランスよくさまざまなメディアを使う」「健康的な生活を意識して利用時間を自己管理する」「人間的なデザインのメディアを意識的に選び活用する」という3つの提案が示されました。これらは指導者からの押し付けではなく、子どもたち自身が考え、納得して受け入れた内容でした。実際、授業後には家庭で「メディアと付き合う3つの約束」を考える課題が出され、生活の中で実践され始めています。
3. 対話を軸とした持続的な成長へのまなざし ― 参加者との議論から見える展望
授業後のディスカッションでは、デジタル・シティズンシップ教育研究会のメンバーをはじめとする参加者から、谷口先生の実践に対して多くの賛同と深い省察が寄せられました。特に注目されたのは、「自己コントロール力の育成」という視点と、「保護者・教員・子どもがともに対話する姿勢」の重要性です。
JDiCE副代表の豊福晋平氏は、谷口先生の実践が従来の情報モラル教育とは異なり、「一方的なルール指導」ではなく「子どもが自ら考え、選び、調整する力」に重きを置いている点を高く評価しました。また、JDiCE理事の林一真先生は、「子どもが正しく間違えること」を受け止める教師の姿勢や、柔軟で持続可能なルール形成の重要性について言及しました。これは、メディア利用における規制強化の是非を考えるうえで、実践的かつ現実的な示唆に富んだ意見でした。
また、JDiCE共同代表の坂本旬先生は、谷口先生の実践が「メディアデザインを意識化する」という高度なリテラシー教育であり、その意義が「子どもと大人の対等な関係による学びの構築」にあると述べました。メディアをめぐる議論において、子どもの視点と大人の視点をすり合わせる対話の場が設けられることは、まさにデジタル・シティズンシップ教育の核心に位置づけられています。
総じて、本実践は「子どもを信じ、任せ、共に考える」ことを体現したものであり、その背景には、保護者や教員が「共通の市民」として対話に参加するという姿勢がありました。これは、情報活用能力や自己調整力といった学力の基盤となる力を育成するだけでなく、学校という場を「学びの共同体」へと深化させる可能性をも示唆しています。
